今回の本はかなり内容が詰まっており、どう感想文に書き起こそうかと迷ったところが本音である。
数日考えた結果、
の3点にしぼって書くことにした。

そもそも哲学とは何なのであろうか
そもそも哲学とは何なのであろうか…
本書は哲学とは安心や真理を求めるという結果に目的があるのではなく、その過程にこそ本質があるという。
これは裏を返せば、哲学とは幸福になるための手段でも、人生に完璧な法則性を見出す魔法のような存在ではないということだ。
仏教やさまざまな宗教またはいわゆる一般常識においての感覚でも、ある一定の状態へと収束することが、自然な状態であるという認識がある。
しかし、哲学とは収束した結果をさらに踏み台として次へ進む。
自然であるように見えてるものを疑うことが哲学の本質であるというわけだ。
終わりのない連続的な営みが哲学なのである。
しかし近代社会においては、ある特定の完璧なる何かが存在しそれに向けて切磋琢磨するという行動が一般的で、より支持されている。
元来あった宗教的、非合理的な仕組みに変わって現れたより先進的で合理的であるとされる近代的な仕組みの多くも実は本質的には(収束先を求めるということにはおいては)大きな違いはないと捉えることもできる。
本書はたとえそれが科学的、自己主義的であっても元来あった宗教的な育みと本質的な違いはないと説明する。
さらに、現代には近来の社会の中に不完全さを見出し、その解決策や新たな理想郷を”自然”的なものに求める傾向がる。
しかしそのような発想は今に始まったことではない。
本書は今は失われた過去の壊れていない、侵されていない理想郷へ戻るといった思想はキリスト教でいうエデンの園へ戻るのと似たようなものであると説明する。

自然的であることの重要性を説いた哲学者
また理想郷についての議論は宗教だけの中の議論ではない。
本質的には人の理想についての議論である。
有名な哲学者もより理想的な生き様とはどのようなものであるかについて考えを巡らしている。
フランスの哲学者であるルソーは人々が社会を成し、文明を築き上げていく過程で、元々人々の間にあったあった「哀れみ」が失われ、私有財産の観念と同時に人間同士に不平等が生まれたのではと考えた。
ルソーは文明を保ちつつも、「哀れみ」とともにある生き方へと近づこうとした。
本書には以下のようにある。
ルソーに言わせれば「自己」を所有する「文明人」と違って「未開人」は、「理性」を働かせて自分の現在置かれている状況を反省的に捉え返したりしないし、(ましてやプラトンの洞窟の囚人のように)崇高な真理を求めたりしない。したがって自らの不幸を嘆いて自殺しようとしたりしない。また他の人間との関係においても、自らの利益を図るために巧妙な計算をめぐらせたりしない。
その意味で、「善/悪」という観念がないのである。
〈宗教化〉する現代思想
「理性」が未発達の「未開人」においては、自/他の違いを意識し、自分の身〝だけ〟を守ろうとする「自尊心 amour propre」の働きを、「哀れみ」が緩和してくれる。
「哀れみ」というのは、母親がわが子を守ろうとする時に、理性的に思考する前に、体が 咄嗟 に動いてしまうような、自然に発動する感情である。
そしてそのような状態においては「哀れみ」が法律、習慣、美徳の代わりとして現れるととく。
しかし、このような思考は我々がかつてはいわゆる罪のない、穢れのない生活を送っていたという基礎のない思考の上に成り立っている。
つまり、一歩罪がない状態や穢れのない生活などについて考え始めると良さげに見えていた概念も実は感覚的によく見えていただけで、理論的な基礎がないことがある。
さらに思考の実現への一歩として哀れみを求めることは共感を求める行動の活発化へと影響を及ぼす。
これは至極人間的、温かみのあるような行動に見えるが,いわゆる思想家、哲学としてこのような流れを介してみると、哀れみが理性よりも重要視されるのは自然的であるためである。
理性よりも哀れみがより自然的であるとする思考も
「自然的」いう大きな概念の上に成り立っているものであり、繰り返しになるが一歩踏み込むと漠然とした何となくの感覚によって作り上げられたものであることが多い。

人の思考、生活を支配するジレンマ
「形而上学」
しかしこのような議論をする前にそもそも、人の思考、人の世界観そのもに逃れることのできない、しがらみがあることを本書は強調している。
西洋の哲学史において、人間の知覚において認知することが不可能であるようなものをめぐる議論を「形而上学,metaphysics」と呼ぶと本書は説明する。
人とは何かについて考えたり宇宙の仕組み、理想郷についての思考をめぐらすようなことである。
しかしこのような形而上学的な思考は必ずしき、いわゆる難し議論に限った話ではない。
たとえば日常に存在する数々のルールや、
「言葉」という単語すらも、形状学的な働き無くしては語ることはできない。
言葉という概念は言葉を言葉たらしめている定義によって理解されているわけではなく、言葉という単語そのものによって何となく、理解されているからである。
またもしくは、虹が七色であるという概念も、虹というものを形而学的に受け止めているためとも言える。
そもそも虹が何色でできているかなど分けれるものなのだろうか,,,
さらには文化に感銘を受けたり音楽を聴いてうっとりすることも、いわゆる形状学的な働きによるものなのである。
人が自身の頭の中に持っている全てのものに対して影響を与えるもの、それが形而上学であり本書は「超自然的な前提」と呼んだ方がしっくりくるかもしれないと説明している。
これはたとえば、社会の仕組みを心理学的な枠組みを使って表すといった行動も
いわゆる「心理学」を複数の事柄を説明できる不可思議なあるいは「その場においての超自然的」存在へと変化させることなくしては行えないことを表している。

形而上学からの抜け道はあるのか
このような形而上学への問題に向き合った有名な哲学者の1人がハイデガーである。
本書は以下のように説明している。
ハイデガーは、プラトン以降の西欧的な知のあり方を支配してきた――と少なくともハイデガーが考える――「形而上学=超自然的な前提」の正体を明らかにし、〝自分たち〟がこれまで拠って立っていた基盤をはっきりと自覚することで、それとは異なる新たな「形而上学=超自然的な前提」への道を開こうとしたわけである。
自分たちを規定するものを知ることが、それとは異なる〝何か〟の可能性を知ることに繋がるわけである。
〈宗教化〉する現代思想
ではハイデガーが解体しようとしたプラトン的な形状学とどんなものだったのか。
本書は「精神/物質」などといった二項対立図式がプラトン的な形而上学の特徴の一つであり、論点の一つとなっていたと説明する。
このように物事を二つの極に分けるような思考は
「人間の意識(精神)は肉体(物質)をどう動かしているのだろか?」
「人(精神)は自らの外にあるもの(物質)をどう見ているのか?」といった疑問などを生む。
しかしこのような二項対立図式も、
対象としているものが本当に存在しているのか
正しい二項対立図式として成立しているのか….
それらのものはただ人が勝手に作り上げたものでしかないのではないかと考え始めると基礎を失う。
しかし、それでもこのような二項対立図式に変わりうる思考方法が存在するのだろうか。

二項対立図式でない思考方法
そのことについて考えた人物として本書はマルクスを挙げている。
マルクスは全てのものは「物質の運動」によって定まり、精神も物質の動きの表れであると説明した。
そのため物質が動くことにより生まれる生産的な働きである経済に焦点を当てたのである。
経済が社会、文化などの土台となっていると考えたのだ。
さらに時代の動きも、精神的、観念的なものではなく社会が持つ物質的側面が矛盾を作り、いわゆる革命によって次の時代へと進むと考えた。
また物質的な働きによって観念が生まれると考えたため、観念を基礎として生まれた宗教的な思考に批判的であった。
人の観念により物質的な働きが促進されるのではなく、物質的な働きにより人の観念が形成されると考えたからである。
しかしこれは「物質の運動」といった魔法のような存在を新たに作り出しているだけで「神の法則である」というの同じようなものになってしまうと本書は説明している。
物質の運動で全てを説明しようとするとある種のこじつけが生まれてしまうことがわかる。
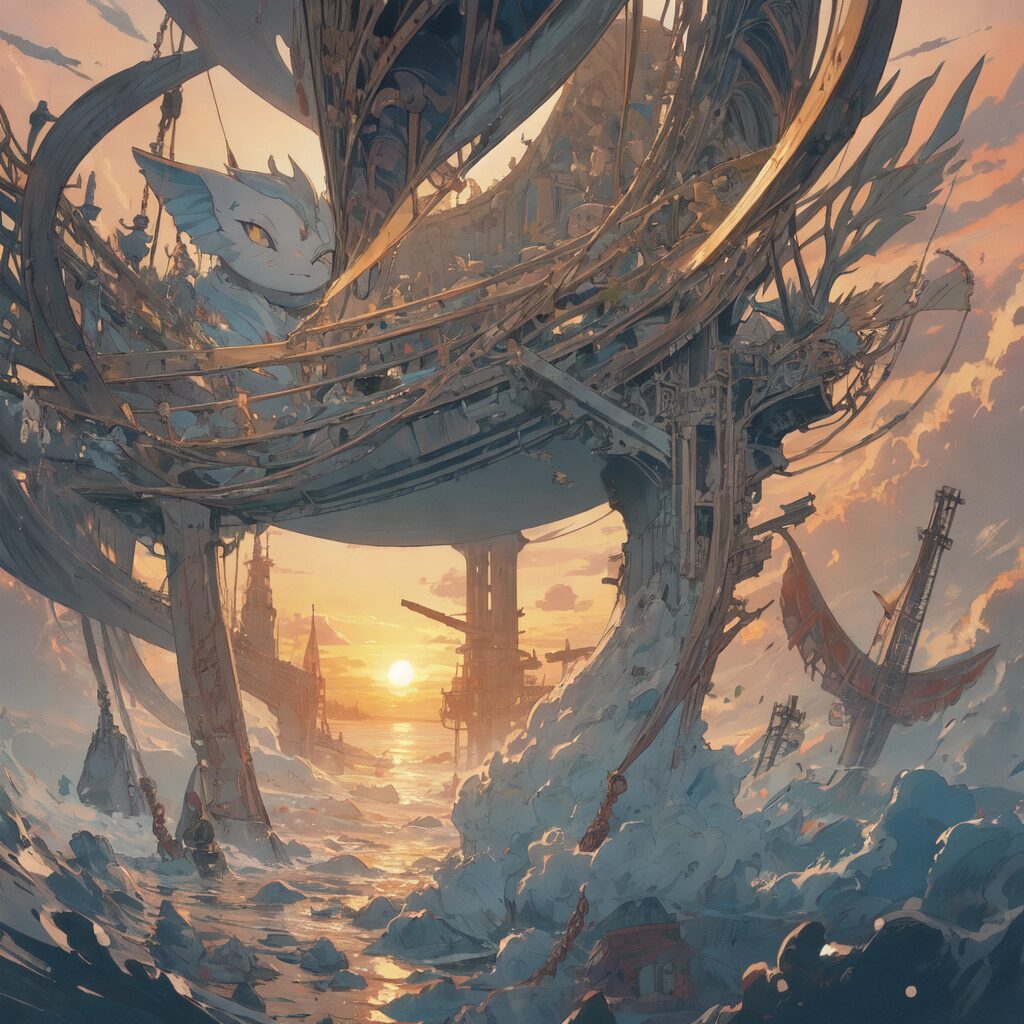
哲学と宗教
哲学的であることと宗教の関係
哲学的な育みは擬似宗教的なものを生み出しやすい。
何かすごいもの、すごい論理を作り上げそれを用意て全てを説明する。
もしそのような理論がその理論を知らない人たちに良い影響を与え、「救い」を差し伸べることができるという考えが生まれれば、それは布教と似たようななものであるかもしれないと本書は書いている。
本書は哲学において、結論として見られるような発言はその場においての過程であると書いています。
そもそもなぜ哲学が近来ここまで注目を集めるようになったのだろうか
本書は以下のように説明している
「哲学という営みが、伝統的な宗教の影響が弱まって不安が高まっている社会において、宗教に代わって、人々に真理、理想を提供し、少しばかり安心させる機能を担っているからである」
さらにそのようの状況の中では真理、理想の提供に対しての期待のみではなく、その場において今は失われてしまったように見える共同体が新たに(真理、理想的な枠組みを通して)現れるのではないかという期待を人々は持つ。
つまり安心感や拠り所として哲学に注目が集まり、そのような流れは哲学が持っている以上の期待を持つ。
しかし哲学とは現実の中においての実行を想定されていない。
なぜなら哲学は見切りをつけることをしないからだ。
実践家と哲学者は違うと本書は説いている。
話が少し流れてしまったがハイデーに戻りたい。
本書は以下のように説明している。
ハイデガーは、プラトン以降の西欧的な知のあり方を支配してきた――と少なくともハイデガーが考える――「形而上学=超自然的な前提」の正体を明らかにし、〝自分たち〟がこれまで拠って立っていた基盤をはっきりと自覚することで、それとは異なる新たな「形而上学=超自然的な前提」への道を開こうとしたわけである。
自分たちを規定するものを知ることが、それとは異なる〝何か〟の可能性を知ることに繋がるわけである。
〈宗教化〉する現代思想
このことについて本書はハイデガーがフライブルク大学で行った講義を元に説明している。
ハイデガーはその講義でプラトンの「洞窟の比喩」示した真理観についての解説をしている。

洞窟の比喩とは
洞窟の比喩とは
地下の洞窟に生まれた時から鎖に繋がれ外の世界を見たことのない人が住んでいる。
彼らは頭の向きを変えることができなく洞窟の壁しか生まれた時から見たことがない。
彼らの後ろでは映写機のようなカラクリがあり洞窟の壁に映像を映している。
そのため洞窟の囚人は壁に映った作り出された映像(本物でない)をそのものの真の姿だと思っている。
もしその中の囚人の1人が鎖を時、その洞窟の中のカラクリ、ひいては太陽の光の下に現れる外の世界を見たらどうだろうか。
最初は明るさのために目が眩むかもしれない。
しかしやがて新しい太陽の下での暮らしに慣れ、洞窟での生活には戻れないと思うのではないだろうか…
洞窟に戻って他の仲間に外の世界のことを説明して、外に出れるように手助けすること、皆を導こうととすることを「啓蒙主義」と呼ぶという。
しかし実は太陽の外に出た囚人も実はまだ洞窟の中にいるのかもしれない。

真理が「真」であるという考えはプラトン以降に生まれた
ハイデガーが考えたプラトンのいう「真理(アレテイア)」の意味 は「正しさ」と「隠されていない(露出している)」ということである。
ハイデガーは本来「アレテイア」とはそれまで隠れて人目につかなかったものが顕になること、あるいは顕になった度合いであったと説明している。
つまり、いまだ隠れているものが既に現れているものよりもより真理に近いという考えはなかったのである。
同時に今あるものが「偽」でいまだ現れていないものが「真」であるという考えもなかったと本書は解説する。
真理(アレテイア)とは本来、今まで顕になっていなかったものが顕になる(隠れなきものになる)という意味の言葉だったのである。
しかし時代が下るにつれ「今は隠れて見えないものが正しく、今見えているものは偽りである」という二項対立図式的な意味合いを真理(アレテイア)は含むようになった。
さらにそのような対立図式の中において「偽」として認識されたものは切り捨てられるようになった。
さらに、ハイデガーは真(正)/偽」の二項対立と結び付いた「真理」観が、西欧人の物の見方を狭隘化しているという考えを展開したと本書は説明している。
つまり「正しいもの」と「誤ったもの」を別け、「誤ったもの」として認知されたものを徹底的に排除する流れである。
本書は以下のように説明している
ハイデガーは「洞窟の比喩」を、ギリシア的な「アレテイア」観が、西欧近代を特徴付ける「真(正)/偽」の二分法の「真理」観へと移行していく第一歩として位置付ける。
元囚人が鎖を解かれて、洞窟の上方に上っていき、太陽の光それ自体に触れるようになるにつれ、それまで彼の目に入って来なかったものが「顕わになってくる」という意味で、囚人はギリシア的な意味での「アレテイア」経験をしていると言える。
〈宗教化〉する現代思想
「向きを変える」ことによって、それまで見えて来なかったものが、顕わになってくる。
そこには真理や「真(正)/偽」は存在しないのだ。
しかし洞窟の比喩ではやがて洞窟の外にでは囚人は洞窟に戻り他の彼らを説得し外の世界に出るように促すようになる。
本書ではその時点で話の焦点のずれが起こっていると書いている。
善のイデア」の光の下で見た「正しいもの=真理」を、依然として洞窟に繋がれている他の囚人たちにいかに伝えるかというところにシフトしている。元囚人=哲学者は、「正しさ」としての「真理」を不動の「物」のように所有する〝正しい人〟になってしまっている。
ハイデガーはプラトン以前の古代ギリシャ世界においては「アレテイア」は隠蔽されているものと、顕になっているものとの相関関係によって生まれるもので、絶対的な正しさを示しているわけではないととく。
太陽の下において現れた世界とは太陽の下において現れただけであり、太陽以外の影響下によっては違う世界観が現れることも当然ありえるわけである。
そのうで自身が依然として洞窟の中にいることを自覚するべきだとハイデガーは主張した。

「有る」ことを有りあらしめているもの
ハイデガーは「洞窟の比喩」の論理の不適さを指摘しているが、光の比喩は否定していない。
洞窟の比喩において光の役目をしていた太陽(洞窟の映写機も)は、「真」「偽」を決める基準から生まれた比喩である。
ハイデガーはさらにそこから光が存在を写しだす、存在を認識させるものであるのならば、光こそが存在の本質であると考えた。
つまりあらゆるものは、ある光によって存在が認知されたものであり、光の差し方によって、現れたり消えたりするという考えだ。
何かが「有る」ことを保証するものそれが「光」であると考えたので有る。
本書はその上でさらに以下のように述べている
ハイデガーは、「現存在=私」のまなざしに対して、「それまで隠されていた」ものが「アレテイア」として現われてくる状態を、「明るみ Helle」と表現している。
ある特定の事物が顕わになるというだけでなく、その事物の現われをきっかけとして、その背後に「あるもの」、つまり万物を有らしめている「存在」それ自体のことに気付くようになることが、「私=現存在」にとっての「明るみ」である。
「明るみ」とは、「私=現存在」が、その都度現われてくる(私以外の)他の事物との遭遇を通して、「存在」それ自体に関心を向けるようになる場である。
〈宗教化〉する現代思想
明るみについて以下のように述べている
この「明るみ=伐採による空き地」こそが、「私=現存在」のまなざしの中で、「存在」が自己を開示する場なのである。
ただし、伐採を主宰しているのは、「私=現存在」ではなく、「存在」それ自体である。「私」自身も、「存在」による伐採=露呈によって「明るみ」に立たされている一存在者にすぎない
〈宗教化〉する現代思想
その中でハイデガーは言語による「存在」の表現に限界があることも示している。
本書には以下のようにある。
ハイデガーは一九三〇年代後半以降のいくつかの論考で、「存在」それ自体からのメッセージをドイツ語に〝翻訳〟してドイツ人にとっての「存在の明るみ」の範囲を確定したのは、ロマン主義時代の詩人ヘルダリン(一七七〇‐一八四三)であると主張している。
何故なら、ヘルダリンが、ドイツ語によって「存在」を表象できる限界を探求したからだという。
本書の筆者によるとヘルダリンの詩の原文は日本語訳とは異なり、混沌としているとある。
その混沌の中にハイデガーはドイツ語という言語の中で思考することを運命づけられたドイツ人にとっての「明るみ」があると解釈したようであると本書は説明する。
これは面白い(もしくは強引な)解釈とも言えるが、ヘルダリンの詩があたたかも「存在」という神のようなものから「明るみ」という掲示をどうにかこうにかドイツ語という枠の中に収めたものとして紹介されている。
ヘルダリンの詩が超自然的な存在(神)の意志を反映しているような神秘主義的な雰囲気がある。

キリスト教の世界観
じつは、「存在」と「言語」のような構図はキリスト教にも存在するという。
キリスト教はプラトンのイデア論の影響を反映するような形で人間の肉体が属する「地上の王国」と霊(精神)が属する「天上の王国」という概念を作り上げた。
「地上の王国」は不可避的に罪の法則が支配的になる「悪」であるのに対し、
「天上の王国」は神につながる善の領域であると本書は説明する。
「善のイデア」のもと理想の国家を作り上げようとするプラトンの構想は実現しなかった。
それに対しキリスト教は「地上の王国」で完璧なる国家を作り上げることは最初から不可能であるとした。
その代わりに、「地上の王国」の上で神の意思を代理するのが教会であるという立ち位置を築き上げたという。
つまり、「天上の王国」の完璧さを示しながらも「地上の王国」で実際に起こることの責任を負う必要がなくなったのである。
このように純粋な「真理」を求めるプラトン的な思考が強いのがキリスト教でり、中世のスコラ哲学の形成に大きく関わった。
しかし、いわば「真理」の化身であるイエスを人々はなぜ受け入れず殺してしまった。
ではなぜ人々はイエスがまさに「真理」そのものであること、イエスの言葉が真理であることに気づくことができなかったのだろうか。
「真理」が真理として人々に影響を与えなかった理由は何なのだろうか。

キリスト教は人が完璧であれない理由を持っている
それは人の持っている罪のためであるとキリスト教は説明する。
人間の体は霊のための器にすぎない。
そのため、悪により易々と侵入されしまう
それがエデンの園で罪を犯し楽園を追放された人間が受け継いできた「罪」であるというのである。
そのため人々は悪簡単に取り憑かれ惑わされたがためにキリストを殺してしまったのだ。
しかしイエスは自らの肉体を持って十字架にかけられ、肉体が滅びることで人類の罪を贖い、霊が悪に打ち勝つようにしてくれた。
そのため人類は霊(精神)によって真理(イエスの言葉)とつながることができるようになったのである…とのことである。
人間を「霊」と「肉」に分けるという発想はプラントも行っており、「霊」が
「肉」よりも優れているという考えも一致している。
本書はこのような「善=霊/悪=肉」二分法的な考えをキリスト教に位置付けるのに大きな役名を果たした人物として初期キリスト教の伝道者パウロについて述べている。
『新約聖書』には、彼が書いたとされる、信仰者のあるべき姿について論じた十三の「書簡」が含まれている。
その中で特に重視されているものが「ローマ人への手紙」という章である。
パウロはその章で「霊(精神)」により「肉体」に宿る「悪」の法則を克服することをキリスト教の信仰の課題としていると本書は解いている。
キリスト教には「終末論」が存在する。
この「終末論」を前提としたキリストキリスト教的な歴史観を体系化したのは
初期キリスト教の最大の教父として知られるアウグスティヌスである。
「終末」は「最後の審判」の日であり、死者も生き返り神の裁きにより、天国か地獄に行くかを振り分けれるという。
「最後の審判」により救いを受ける身はキリスト教の信仰が重要であると言っているとも取れる。
アウグスティヌスが生きていた当時、キリスト教がローマ帝国の衰退を背景として批判にさらされていた。
その批判に対しキリスト教の擁護を目的としてアウグスティヌスが執筆したのが「神の国」である。
彼はその中において「神に国」と「地の国」の総合作用により歴史が進みや、がて最後に「終末」へと至るという歴史観を示し体系化した。
本書は
「光=善=霊/闇=悪=肉」の二項対立図式を通して歴史が進展し、「終末」において何らかの形での〝最終決戦〟に至るという考え方を、キリスト教の歴史観として定着させたのは確かである。この発想が、その後、キリスト教文明圏で生まれてくる様々な哲学・思想に強い影響を与えることになる。
〈宗教化〉する現代思想
と述べている。

なぜキリスト教は
批判の対象となる(ことがある)のか
宗教改革や市民革命などを経て、近代化(=世俗化)のプロセスを歩み出した西欧社会は、表面的にはキリスト教の教義の影響から次第に離脱していったように見える。
仲正 昌樹. 〈宗教化〉する現代思想
しかしその中においても「光=善=霊/闇=悪=肉」の二項対立図式を通して歴史が「終末」へと動いているという考えは存在しているという。
「啓蒙」的な思考が「真理」を求め「理想」を目指すというプラトン的な思考はキリスト教とも共通点があることをすでに書いた。
しかし啓蒙主義者にとってキリスト教はむしろ長年民衆を無知な状態としてきた批判するべき存在であった。
本書は以下のように説明している。
代表的な啓蒙主義者であるヴォルテール(一六九四‐一七七八)等は、全ての人類が罪人であると強調することを通じて民衆が自分の頭で考えることを妨げてきた教会の横暴を糾弾し、教会の作り出す「闇」から人々を解放することが、人々に本来的に宿っている「理性」の覚醒に通じると考えた。
〈宗教化〉する現代思想
神によってではなく人間自身に存在する「理性」こそが「光」的な存在であると考えたのである。
このような思考は人間の「理性」がやがて、幸せで平和的な社会を作り出すといった近代的な思想を作り出す基礎となった。
だがこの理性という概念も蓋を開けてみると、とても曖昧なものである。
本書はさらに言えばこれは「キリスト教が正しい/理性主義が正しい」といった二項対立構造を作り上げたのち、理性主義が勝利を掴んだだけであると説明する。
ただそれまで人々が真理として扱っていたキリスト教が理性にとって変わっただけであるというのだ。
さらに本書は哲学の中においては、自我そのものについては”あまり”論じられてきていなかったと説明している。
デカルト以降哲学者は、認識をしているものとしての自我とその自我が見ている外の世界との関係性について思考してきた。
カントは物理的な世界からは独立した「純粋理性」についての考えを深めたが、その理性が存在していることは証明していない。
つまり「理性」が何であるかについての考えと
その「理性」が実際に存在するかについての議論は別であり、後者についての議論はそこまでされてこなかったというのだ。
完璧なプログラムのコードのついては考えきたが、そのコードが動く状況や、何によってコードがコードたらしめられているかについてはあまり考えられてこなかったのかもしれない。

理性が何であるかについての議論
本書はカントに続くドイツ観念論においては人々は
精神(主体)」と「物質(客体)」を繋ぐ統一的な原理は何であるかを探求してきた。
と説いている。
純粋な精神世界に存在する「理性」がいかにして、精神世界の外に存在する物事を認識しているかについて思考してきた。
ドイツの哲学者であるシェリングはこの世の根源的なものとして「絶対者」が存在するとしこの「絶対者」を介し「精神的」な存在である「自我」が外界の物事を認識できるとした。
また同じドイツの哲学者ヘーゲルはシェリングが直接的に全てを形作っている「絶対者」と「自我」を結びつけたのに対し
「絶対者」は「歴史」の中において「自我」との関係性が現れると説いた。
シェリングの考えた「絶対者」はこの世の全てに通ずる法則であり、その法則と繋がっているものが「自我」であり「理性」である。
しかしヘーゲルはそれとは変わり「絶対者」と「理性」は完璧な関係性を持っていないと考えた。
しかし逆にヘーゲルはそこから人の「理性」の行動による結果として現れる「歴史」に完全さへと向かう法則性が現れると考えたのだ。
つまり「理性」こそが「歴史」を進める鍵であり、その「歴史」に人間が見出すことのできなかった「絶対者」の意図、真理が隠れいている(年々顕になってくる)と考えたのである。
しかし、このような考えもやはり形而上学的な枠組みの上に縛られている。
以前のべたマルクス論はこの「絶対者」が「物質」に取って代わったと捉えることもできる。

そもそもなぜ理性は
重要視されているのか
本書は今日においてなぜ理性がなぜ重要視されるのかについて以下のように説いている。
「近代市民社会」は、万人に内在する「普遍的な理性」に基づいて各人がお互いの――「理性」が宿る――人格の尊厳を認め合うようになり、その相互承認関係から「自由」や「平等」などの基本的人権の諸理念が導き出されてくるので、万人はそれぞれ異なった価値観を抱きながらも平和に共存できるはず、という前提の下に成立している。
〈宗教化〉する現代思想
しかしもしこの考え方が的を射ていたなかったらどうだろうか…
「理性」によって平和な社会になるなどといった保証はどこにも無くなってしまうのである。
さらに本書は真理を求めるということは言わば「普遍的理性」を見つけ出し、そこに至る道であるとも説いている。

そもそも「理性」は存在するのか
「理性」や「自我」を中心とした議論を展開することの限界を論じた人は哲学界にもいる。
本書は例えば、カントは「理性」はこの世界を完全に認識することはできないとした、
また英国の哲学者であるヒュームは「自我」が持続的に存在することを認めなかった。(寝てる間に自我はない(と言える))
さらに自我とは単なる知覚の印象によって生まれるものとし、そこから派生する理性も重要性を帯びないとといた。
さらにヒュームは理性とは動物的な本能の一部であると考えた。
動物も周囲の状況などに合わせ、考えを巡らせたりすることができる、理性は人間だけに備わっているものではないとヒュームは考えたのだ。
さらにヒュームはカントが人間は「道徳法則を志向する「実践理性」によって物質的な欲求を抑え、自由意志に基づく行動ができるとしたのに対し、ヒュームは理性の一部である、「理性」にそのような能力はないと考えた。
ヒュームは「理性」はむしろ根本的な本能により近い「情念」に打ち勝つことができず「情念」に奉仕すると考えた。
ヒューム哲学について本書は以下のように説明する
ヒューム哲学では、〝道徳の法則〟だと我々が思っているものは、自然界に〝因果法則〟が見出だされる場合と同様に、習慣を通して、つまり他の人間との相互関係における経験の反復を通して形成されてくる。自己自身の利益を増進し、相手との間で「共感 sympathy」が生じるような振る舞いを、各人の「情念」が志向するようになり、それに伴って「善い振る舞い」が社会的にパターン化されてくる。
〈宗教化〉する現代思想

理性主義への問題提起と
ポストモダン主義
理性主義への問題提起から生まれたのが、ポストモダン思想である。
本書は以下のように説明している。
ポストモダン思想は、「普遍的理性」があらゆる「人間」に宿っており、それに基づいて全人類を包括するユートピア的な共同体を構築することが可能であるという形而上学的な想定が、人々から多様な生き方の可能性を奪い、不自由にしているのではないかという問題意識を起点にしている。
近代的理想主義や、マルクス主義、そこから派生したと言えるリベラル左翼は問題が起きるのその問題は、完璧な理想による統治が整っていない、もしくは理性的な欠陥がどこかにあるのではと考えるようになる。
そのような考えは、過ちを見つけるとともにより行動な理性的行動、仕組みを作ることを求め、自分以外の人々に対しより理性的であることを強調する節がある。
また歴史上を見ても「理想」を掲げた上で独裁的な統治が生まれたことは数少ない。
ポストモダン思想は、そうやって〝理性のより真なる現われ〟を追求し続ける弁証法的な発想こそが、価値観の異なる他者に対して「真理」を押し付け、順応させようとする「理性の暴力」であると考えた。

理性主義は不条理なモノの排除の上に
出来上がったとも捉えられる
本書はフランスの哲学者であるフーコは著書「狂気の歴史」において以下のような考えを展開しているという。
『近代市民社会において「理性/狂気」の境界線が二項対立的に鮮明となり、標準化された「理性」の枠内で説明できない〝不条理なもの〟が「狂気」として社会の表舞台から排斥されることによってデカルト流の「理性」的な「自我」が成立した、という議論を展開している。』
〈宗教化〉する現代思想
西洋近代的な理性主義は理性から外れたとされるものを弾圧、排除するというある種の社会的圧力により人為的に作られてきたと捉えることもできる。
フーコはそのような正常で規範性に従うよう人々の内面で作用する力を「司牧権力」と呼び、
「司牧権力」は外部から内面のケアとして個人に介入し規範性に主体性を持って従うような仕組みを作り上げていると説いた。
さらに精神分析の創始者であるフロイトもそのような、常に「私」「自我」を見つめ、社会規範から外れないように監視している存在を「超自我」とよんでいる。
またこのような流れがキリスト教の告白などの儀式の流れを汲んでいることもそれだけに理由を求めるのは的違いであるが、確かであると本書は説いている。
さらには「告白」などの儀式や「反省会」などもそのグループや社会的な規範の内面化を促す良い手段である。
日本の学校教育などで自発性の発達のためとして「反省会」などを行なっているがもしかしたらそれは周りの意図を汲むことをより褒めのかしてるだけなのかもしれない。
しかしそのような行いだけを取り出してみると、宗教団体で行われていそうなこととあまり違いはないのである。

まとめ
まずはここまで天文学的な確率を生き延びお読みいただいたあなたに感謝をしている。
今回読ませていただいた本書については自分の基礎知識の不甲斐なさ、理解力のなさが浮き上がるような本だった。
このブログも後ほどアップデートする予定である。
しかしいつも通りながら本書のAmazonのアソシエイトリンクをここに貼らせていただく。
踏んでいただけると大変ありがたい….
もしくは「宗教化する現代思想」と検索していただけるとどの検索エンジンでも1番上に出てくると思う・